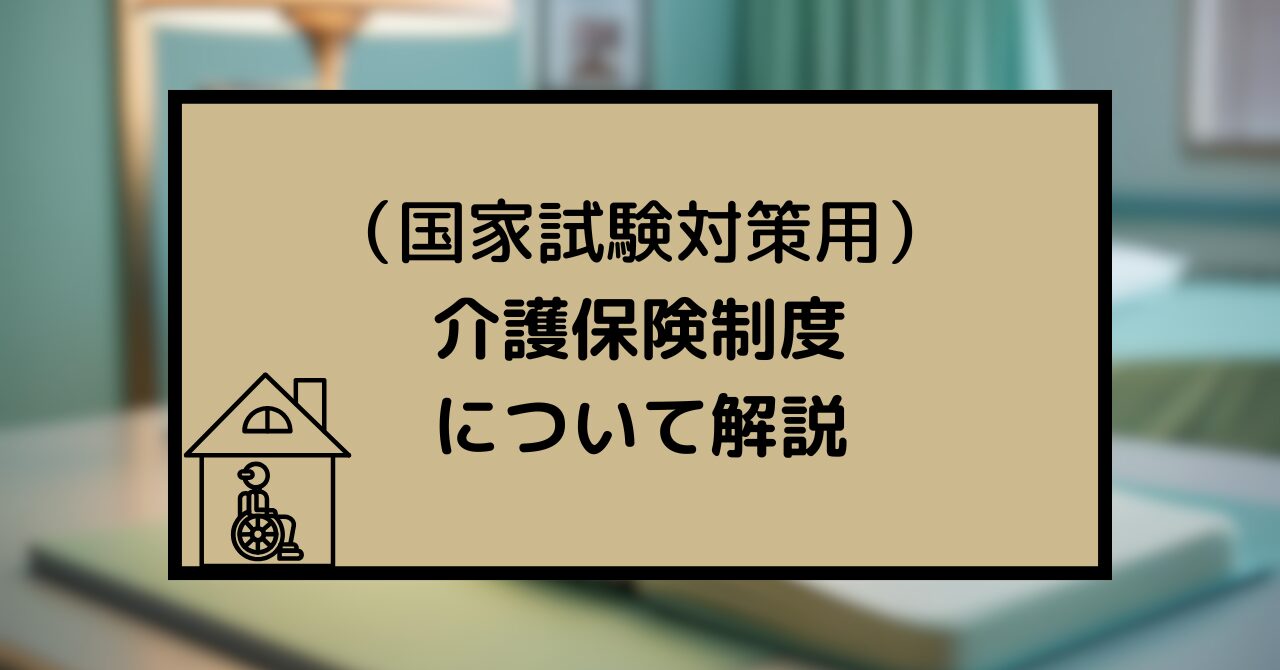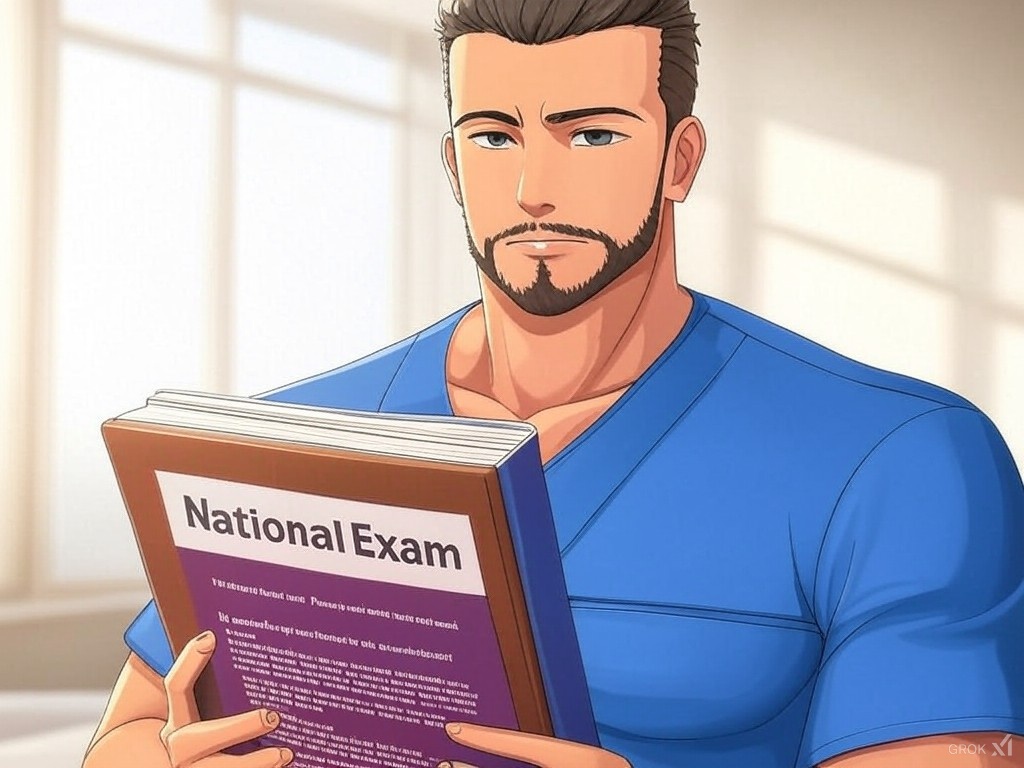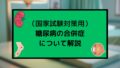介護保険制度は、看護師国家試験でたびたび出題される社会保障制度の一つです。
特に「第1号・第2号被保険者の違い」や「保険者」「サービスを受けられる条件」などは、選択肢で問われやすいポイント。
今回は、看護学生がつまずきやすい介護保険の重要ポイントを、表も交えてわかりやすくまとめます!
🔍 第1号・第2号被保険者の違いを整理しよう
介護保険の被保険者には、年齢によって2つの区分があります。
| 被保険者区分 | 年齢 | 保険料の納付先 | サービスを受けられる条件 |
|---|---|---|---|
| 第1号被保険者 | 65歳以上 | 市町村 | 要介護・要支援状態であること(原因不問) |
| 第2号被保険者 | 40~64歳 | 医療保険と一体 | 16の特定疾病による要介護・要支援状態であること |
🟦 国試ポイント:
- 「第2号は“特定疾病”による要介護状態が条件」となっている
- 保険料は、第1号は市町村に直接、第2号は医療保険に組み込まれて納付
- 介護区分は、要支援1~2、要介護1~5(全部で7段階)
🔍 特定疾病ってなに?
第2号被保険者がサービスを利用するには、特定疾病のいずれかに該当する必要があります。
この特定疾病は、国試でも狙われることがあるので、少なくとも以下は覚えておくのがおすすめです。
🧾 よく出る特定疾病(例)
- がん(末期)
- 脳血管疾患
- 関節リウマチ
- パーキンソン病
- 初老期における認知症
🔍 保険者は誰?認定するのは誰?
保険者:市町村(または特別区)
→ 国試では「都道府県」や「厚労省」と間違える選択肢が多いので注意!
要介護認定:認定するのは市町村
市町村に設置されている介護認定審査会が実施する
📌 国試でよく出るポイント
| よく出る項目 | 国試での出題例 |
|---|---|
| 被保険者の区分 | 「第2号被保険者に該当するのはどれか?」など |
| 保険者 | 「介護保険の保険者は?」→正解:市町村 |
| 特定疾病の理解 | 「特定疾病に含まれるものはどれか?」 |
| 要介護認定を行うのは? | 市町村 |
| 審査判定を行うのは? | 介護認定審査会 |
| 利用負担は? | 1〜3割(最大で何割負担か把握しておく) |
✅ まとめ
介護保険は、社会保障制度の中でも“しくみがややこしく見える”分野です。
でも、「年齢による被保険者の違い」「特定疾病」「保険者」をおさえれば、国試ではしっかり得点できます。
表やフローを使って整理すれば、暗記もスムーズになりますよ。
復習プリントなど、視覚的にまとめて何度も見返せる形にしておくのがおすすめです◎
(参考・出展)
- レビューブック看護
- 看護roo!
- 公衆衛生がみえる 2024-2025