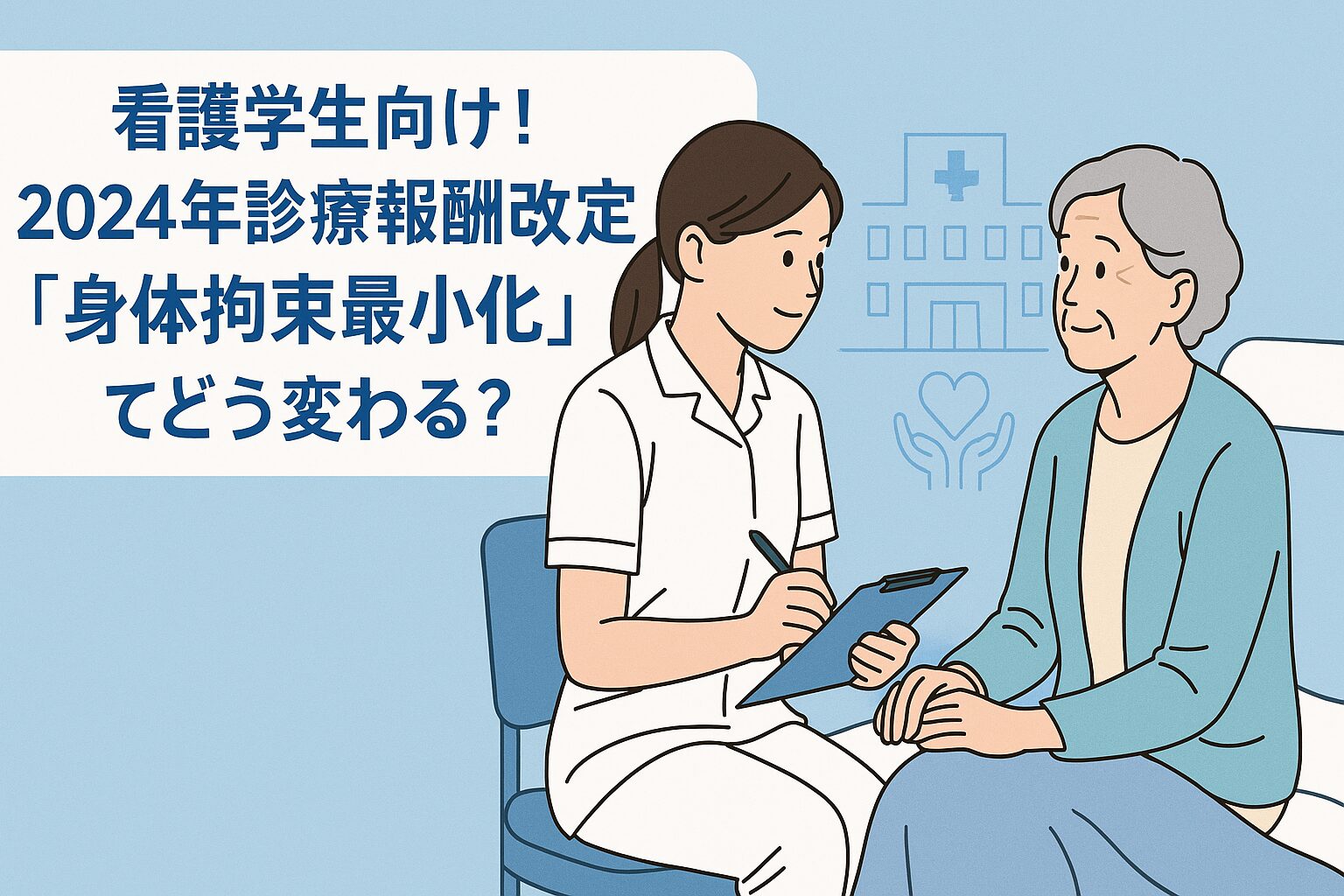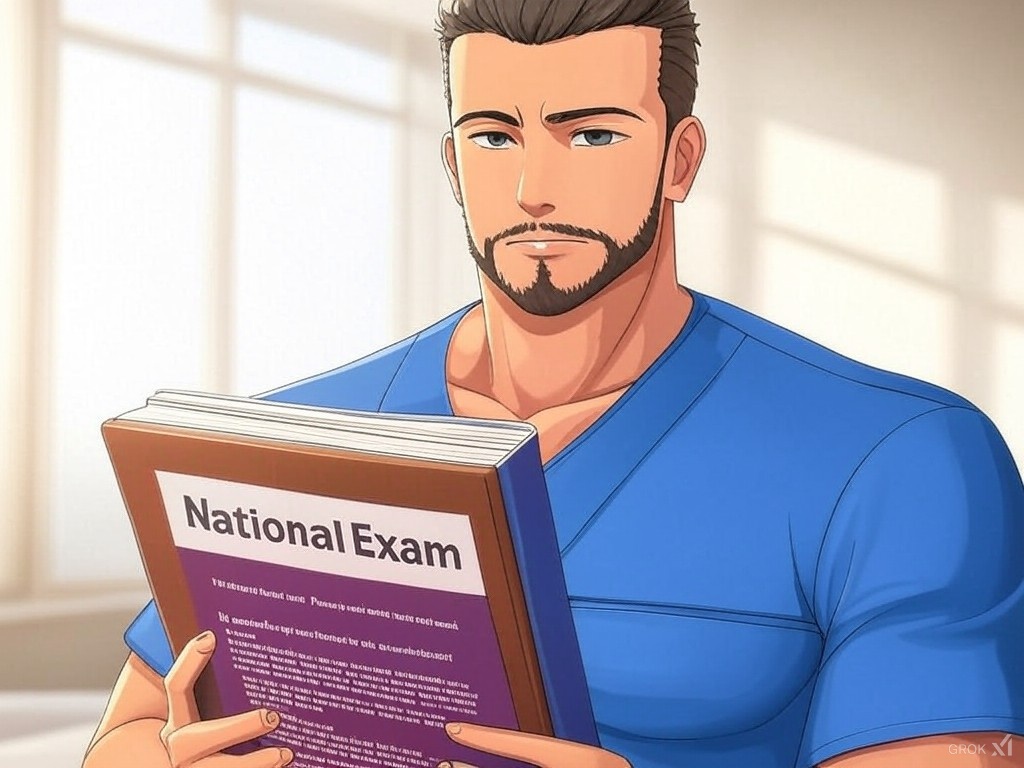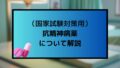なぜ今「身体拘束最小化」なのか
2024年度の診療報酬改定により、医療機関における**「身体拘束の最小化」**が強化されました。
これまでも介護施設では原則禁止とされてきた身体拘束ですが、病院においても“当たり前のように使う”という時代は、終わりを迎えようとしています。
患者さんの尊厳や人権を守る看護が、より一層求められている今、看護学生もこの変化を知っておくことはとても大切です。
背景:制度改定の目的とポイント
身体拘束は、患者さんにとって大きなストレスや身体的負担となる行為です。
今回の改定では、こうした拘束を「できる限り行わない」ことを診療報酬の条件に組み込むことで、現場に変化を促しています。
何が変わった?改定内容の要点
以下が、改定による主な変化です:
| 項目 | 改定内容 |
|---|---|
| 対象 | 急性期・回復期・地域包括ケア病棟など |
| 内容 | 身体拘束の最小化に向けたチームの設置、記録の徹底、方針の明示など |
| 施行時期 | 2025年6月1日から減算スタート(※経過措置あり) |
身体拘束の最小化の基準
「身体拘束の最小化」の基準について、次のように示されました。
- 原則として身体拘束は禁止。ただし、患者または他の患者等の生命・身体を保護するために緊急やむを得ない場合は例外。
- やむを得ず身体拘束を行う場合は、その理由や態様、時間、患者の心身の状況などを記録することが義務付けられます。
- 「身体拘束」とは、抑制帯などを用いて患者の身体や衣服に触れ、運動を一時的に制限する行為を指します。
- 基準を満たさない場合は、入院基本料や特定入院料等から1日につき40点減算されるペナルティが科されます。
ブログ運営者の個人的感想
正直な気持ちで言うと、「大変になるなぁ」というのが第一の感想でした。
ここでは今回の身体拘束の最小化について、思ったことを綴っていこうと思います。
まとまりがない文章になってしまったら申し訳ありません、、
そもそも身体拘束をする理由は?
身体拘束の目的としては、末梢静脈点滴や経鼻胃管などチューブの自己抜去の防止や、転倒転落の防止のために行われることが多いです。
チューブ類は患者の治療の為に必要なもので、それの抜去は治療の中断になってしまうので防止するのが看護師の役割でもあります。
転倒・転落に関しても、それにより外傷を負ってしまうと、更に入院期間が延長され患者への苦痛も増えてしまいます。
外傷の例としては、骨折や急性硬膜下血腫などのリスクがあります。
適切にアセスメントをしたうえでの身体拘束は、医療において必要だと考えています。
現在は身体拘束は最小にしようと取り組んでいる病院はほとんどですが、ICUや急性期などの病棟では身体拘束の割合は多いデータもあります。
看護師の負担が増える懸念
身体拘束をした場合に記録が必須となり、看護師の業務量が増えると考えられます。現時点でも拘束に関して全く記録をしていないことはないですが、今より更に詳細な記録が求められるでしょう。
また病院としても、減点を避けたい為に拘束をなるべく避けるように持っていくことも考えられます。
適切な拘束は必要と思いますが、減点回避で必要な拘束も実施しにくい状況も生まれるかもしれません。
そして抜去や転倒など発生すれば、業務は中断されたりインシデントレポートの記載の業務発生など、やはり看護師の業務負担が増加する可能性は高いです。
まとめ
身体拘束の最小化が、今年の6月から本格的に施工・義務化されます。
これは看護師だけの課題・責任ではなく、病院全体で取り組むべき事象だと思います。
各病棟の体制のやマニュアルの見直し、働き方も考え直す機会かもしれません。また看護師自身もアセスメント能力を養う必要性が出てくるので、全員で一丸となって取り組んでいくのが望ましいなと思っています。
今回は以上です
学習の参考になれば幸いです。