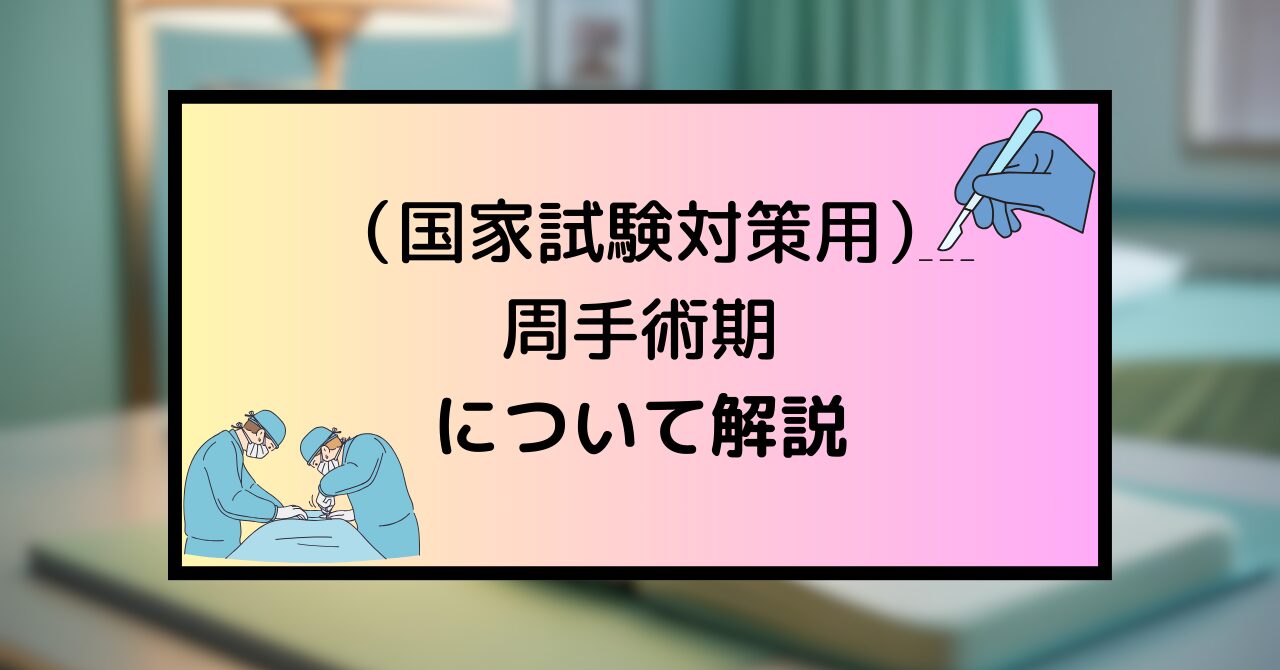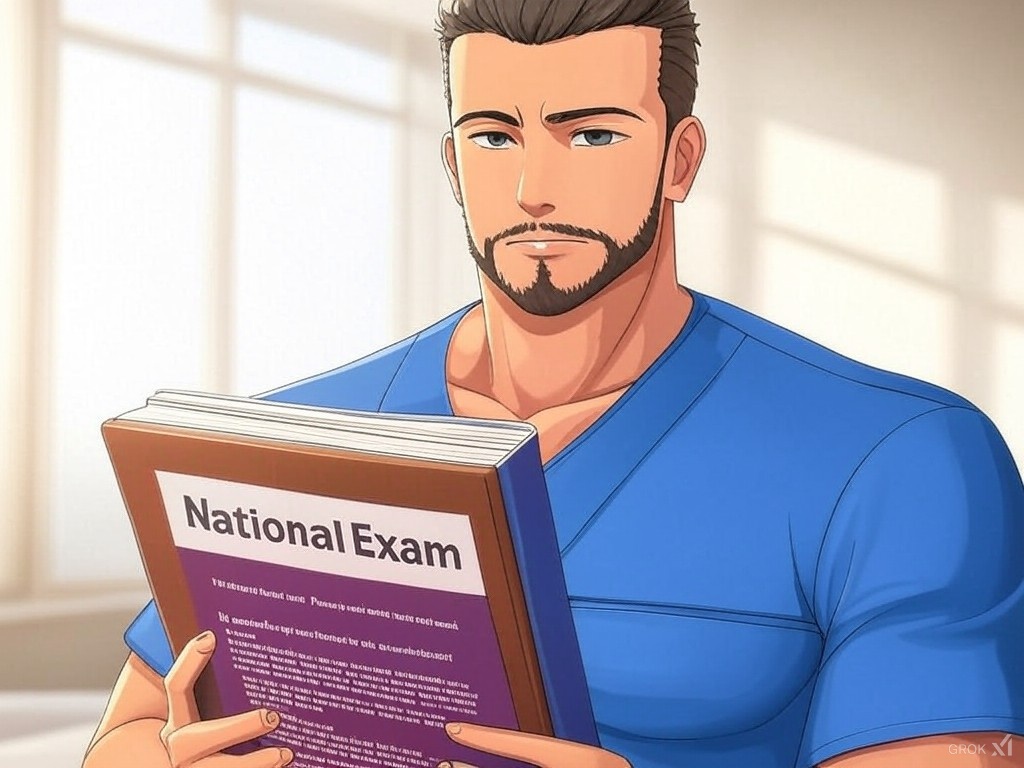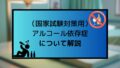周術期の看護は、術前・術中・術後の一連の流れにそって、患者の安全と回復を支える重要な看護の1つです。
国家試験でも当然問われます。各期によって求められる看護も異なります。
この記事では、周術期の3つの時期それぞれでの看護のポイントを分かりやすく解説し、国家試験で問われやすい視点も紹介していきます。
術前の看護
- 術前指導:手術の日時、内容、術後合併症とその予防策の説明
- 術前から口すぼめ呼吸や深呼吸の訓練を実施し、呼吸筋の強化を行う(術後合併症の予防と回復促進のため)
- 高齢者・嚥下障害・肝機能障害などがある患者は、低栄養状態になりやすい。
術後の縫合不全や感染防止のために、高カロリー輸液や経管栄養での補給を行う場合もある - 手術への疑問や不安の解消のための、心理的な援助も行う。

手術内容によって手術部位の除毛や、マーキングを行います。
全身麻酔か局所麻酔かによって経口摂取の制限も変わってきます。
術中の看護
- 深部静脈血栓症(DVT)予防に、弾性ストッキングを着用する
- 褥瘡の発生予防に、褥瘡予防マットを使用する
- 術中体位の固定により、同一部位が圧迫され神経麻痺を起こすリスクがあるため、良肢位を保てるよう体位を工夫する
術後の看護
*周術期の看護で術後の看護が国試で特に問われやすいです。
手術全般で気を付けること
- 創部痛により呼吸が浅くなり、酸素飽和度が低下することがある
└疼痛緩和を行い、呼吸運動・喀痰排出の抑制を防止する - 早期離床を促す。それにより腸蠕動運動の促進・呼吸器合併症予防になる
└長期臥床は肺血栓塞栓症を引き起こすリスクを上げる - 喫煙、糖尿病、副腎皮質ステロイド薬、高齢、低栄養は手術部位感染の危険因子
- *術後一過性のせん妄を発症することがある
- 抜去事故防止のために、抜去できるチューブ類がないか医師に確認する
- 術後は麻酔の影響で無気肺を起こしやすい
└呼吸状態の観察、深呼吸の促し、酸素吸入などで呼吸状態の改善に努める
*術後せん妄とは?
手術をきっかけに、術後に発症するせん妄で、一種の意識障害です。
- 術後数時間で発症し夜間に増悪する
- 術後3~5日後に発症することが多い
- 症状:見当識障害、抑うつ、幻覚、精神運動興奮、睡眠障害など
- 症状は多彩だが、一過性である
- 基礎疾患や手術の侵襲度と一定の関連がある
✅ まとめ
周術期の看護は、各期で何が重要かを明確にして理解することが大切です。
国家試験では、安全確保、早期回復、合併症の予防という基本視点を持って選択肢を判断しましょう。
今回の内容に踏まえ、手術内容によってそれぞれの気を付けるべきポイントも整理しておきましょう。
例えば白内障の手術した患者が術後に注意することはなにか等です。
また手術にあたって休薬すべき薬物もあるため、それも学習しておきましょう。
今回は以上です。
学習の参考になれば幸いです。
【参考・出典】
・レビューブック看護
・看護roo!