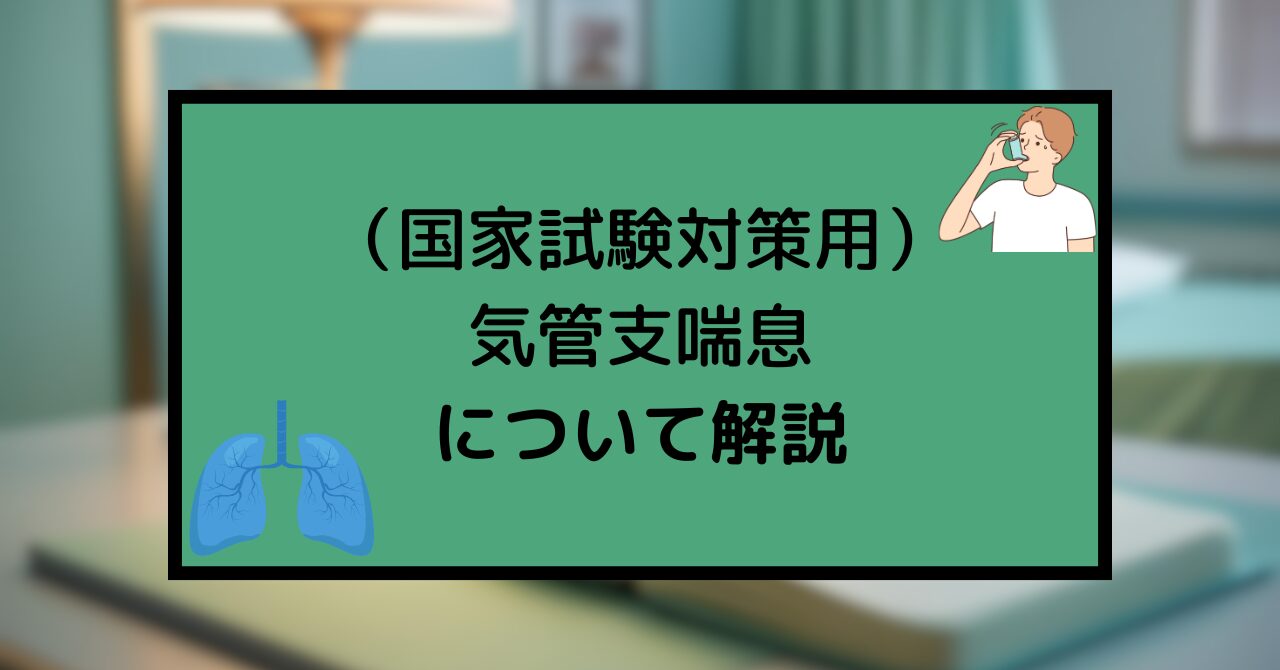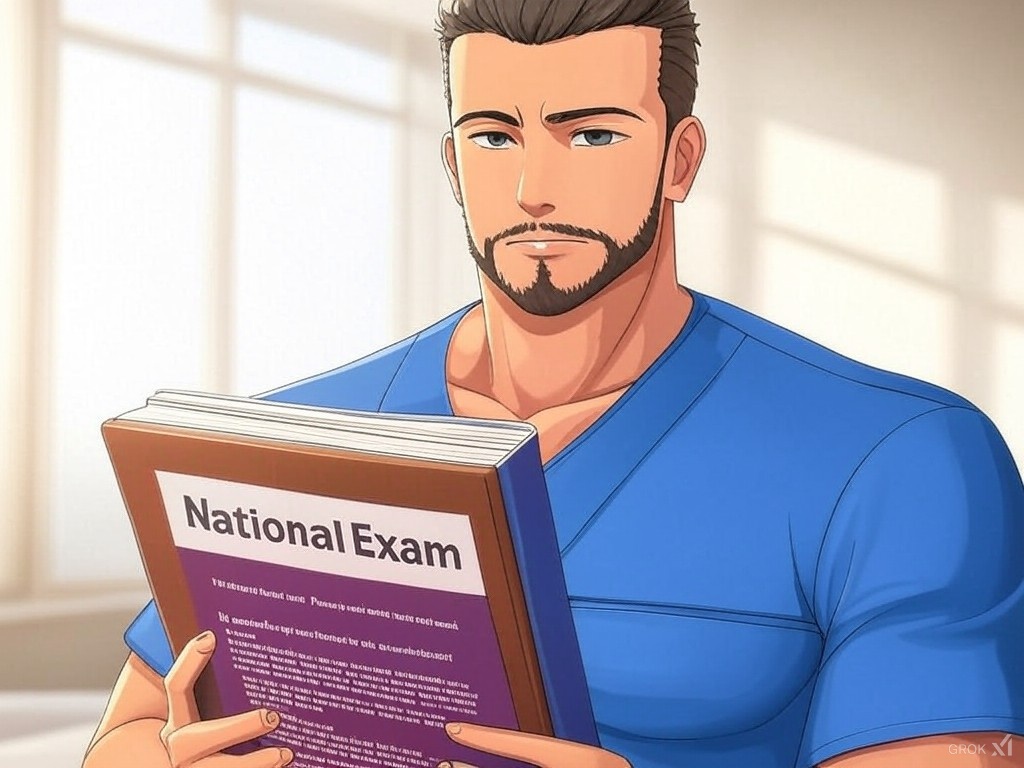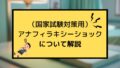気管支喘息とは?
気管支喘息は、気道に慢性の炎症が起こり、気道狭窄や咳嗽で特徴付けられる疾患です。
喘息は小児に多く見られますが、約70%は思春期までに寛解します。
成人になっても続く場合もあり、国家試験では、小児看護・呼吸器疾患・薬理・検査など、さまざまな観点から問われる疾患です。
気管支喘息の原因
アレルギーが主な原因
気管支喘息の多くはⅠ型アレルギーに分類され、ダニ・ハウスダスト・花粉・ペットの毛などのアレルゲンにより、気道にアレルギー性炎症が引き起こされます。
薬剤では、非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)やβ遮断薬でも、引き起こされることがあります。
発症リスク
- 家族歴(遺伝的素因)
- 喫煙(受動喫煙も含む)
- 呼吸器感染症の既往
- 季節(特に秋)
- 時間帯:深夜〜明け方に多い
主な症状と経過
- 呼吸困難・咳嗽
- 聴診で笛声音、呼気の延長(息が吐きにくいため)
- 重症化すると、肩呼吸や起坐呼吸、チアノーゼが発症することがある
寝ている状態(仰臥位)では呼吸がしんどく、身体を起こした状態(起座位、半座位)になることを起坐呼吸といいます。
検査と診断
スパイロメトリー(肺機能検査)
- 閉塞性換気障害を示す(1秒率の低下)
血液検査
- 好酸球↑
- IgE↑(アレルギー体質を反映)
治療
薬物
- 吸入ステロイド:気道粘膜に直接作用する。経口ステロイドに比べ副作用が少ない
- 吸入ステロイドは予防治療薬のため、非発作時にも継続して吸入をする
吸入療法の指導ポイント
- 吸入デバイスの使い方の始動
- 使用後は口をゆすぐ(口腔カンジダ予防)
看護のポイント(国家試験対策)
観察項目
- 呼吸音(喘鳴の有無・範囲)
- 意識レベル
- チアノーゼの有無
- 脈拍・呼吸数の変化
慢性期の看護
- 発作予防のための環境整備(ストレスをためないよう指導する)
- 発作時の対応の指導(起坐位で腹式呼吸や口すぼめ呼吸を行う)
まとめ
気管支喘息は、アレルギー反応による気道の慢性炎症と、それに伴う発作的な症状が特徴の疾患です。国家試験では、疾患の理解だけでなく、看護の観察ポイント、薬剤の分類、検査所見など、幅広く問われます。
特に発作時の対応や吸入薬の使い方など、実習でもよく遭遇する内容ですので、しっかり押さえておきましょう。
今回は以上です。
学習の参考になれば幸いです。
📚 参考・出典
- レビューブック看護
- 病気がみえる vol.4 呼吸器(メディックメディア)
更に理解を深めたい方へ
本記事の参考にも使用した 「病気がみえる vol.4 呼吸器」 は、看護学生の間で定番の国家試験対策本です。
✅ 豊富なイラストと図解で、難しい呼吸器疾患も直感的に理解
✅ 国家試験で頻出のポイントが効率よくまとまっている
✅ 看護技術や解剖生理の復習にも最適
呼吸器疾患の理解を深めたい方は、この1冊があると勉強効率が格段に上がります。
 | 病気がみえる vol.4/医療情報科学研究所【3000円以上送料無料】 価格:4510円 |