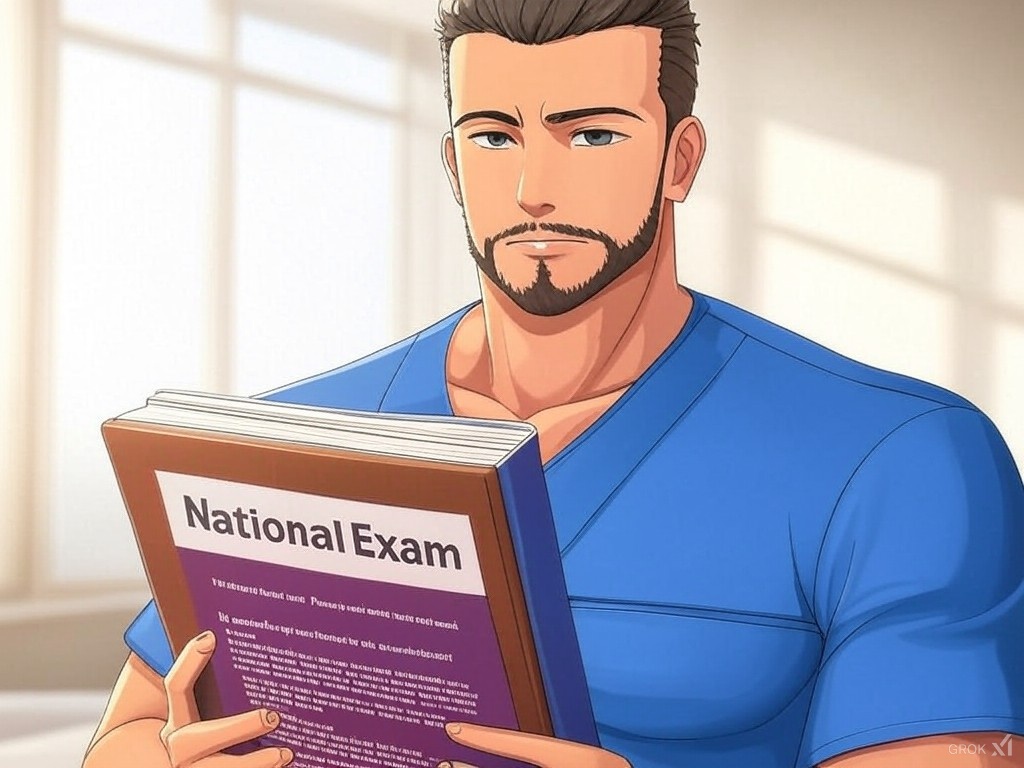抗精神病薬って、結局どんな薬?
精神科の薬って、覚えることが多くてややこしい…そう感じている看護学生さん、多いですよね。
この記事では、看護師国家試験で頻出の抗精神病薬(統合失調症の治療薬)をわかりやすく整理していきます。
抗精神病薬の基本 何に使う薬?
抗精神病薬(抗精神病作用を持つ薬)は、主に統合失調症などの精神疾患の治療に用いられます。
幻覚や妄想を抑える作用と鎮静作用があります。
抗精神病薬には非定型抗精神病薬と定型抗精神病薬があります。
それぞれ以下のような特徴があります。
| 分類 | 特徴 | 例 |
|---|---|---|
| 非定型抗精神病薬 | セロトニン・ドパミン拮抗作用がある | リスペリドン、オランザピン、クエチアピン |
| 定型抗精神病薬 | ドパミンD2受容体阻害作用が特に強い。 | ハロペリドール、クロルプロマジン |
📝【それぞれの副作用】
- 非定型薬:悪性症候群、高血糖、糖尿病患者には禁忌
- 定型薬:錐体外路症状、悪性症候群
次の項目では副作用について具体的に解説していきます。
よく出る副作用とその特徴
抗精神病薬は副作用がよく問われます。
特に以下の2つは、国試の頻出テーマです👇
① 錐体外路症状
・パーキンソン症候群:手の震え、筋固縮
・ジスキネジア:不随意運動
・アカシジア:じっとしていられない
② 悪性症候群
抗精神病薬の服用中や、抗パーキンソン病薬の急激な減量・中止をした際に、高熱や錐体外路症状、自律神経症状などが出現する病態
まとめ|抗精神病薬の全体像をつかもう!
- 抗精神病薬は幻覚や妄想の抑制作用と鎮静作用
- 定型と非定型の違いを理解する
- 「症状と薬の関係」を理解すると記憶に残りやすい!
国試では、上記が問われやすいです。
今回は以上です。
学習の参考になれば幸いです。
(参考・出展)
- レビューブック看護
- こころの健康がみえる